

うんな中学校サイエンスクラブ
うんな中学校サイエンスクラブは、ハニーコーラルプロジェクトを中心に、様々な科学や自然について学んでいます。
うんな中学校サイエンスクラブの商品

ハニーコーラルプロジェクトとは
2020年に恩納村と沖縄科学技術大学院大学(OIST)は、ミツバチの養蜂を行うことで、畑からの赤土流入からサンゴ礁を守る共同プロジェクト『ハニーコーラルプロジェクト』を立ち上げました。
赤土流出は、沖縄県の最大の課題の一つになっており、雨が降ると畑の土壌の表面が浸食され、雨水と共に赤土が河川に流れ込み海に流入します。海に堆積した赤土は、サンゴ礁の白化現象を引き起こす原因になるとも言われています。この課題を解決する鍵を握るのが、ミツバチなのです。ミツバチは花に授粉することで一定の多様性をもたらすため、土壌の吸水性が高まり、赤土流出を抑えることができると考えられています。
養蜂を行うと同時に、赤土流出問題への関心を高めるハニーコーラルプロジェクト。養蜂技術を村内の農家さんに広めていくことで、農家は副収入源を得ることができ、蜂蜜を生産・販売することができるようになります。このプロジェクトを続けていくことで、サステイナブルな農業、環境の利用、環境保全につながっていきます。
村内にて行われているハニーコーラルプロジェクトを、うんな中学校サイエンスクラブにとりいれることで、農業に関する興味を引き出し、恩納村の持続可能な農業、観光、環境を保全する意識を育み、将来の恩納村を担う活動を行っています。
ミツバチとは
ミツバチとは、ハチ目(膜翅目)・ミツバチ科・ミツバチ属に属する昆虫の一群で、世界に9種います。
日本は主にセイヨウミツバチと二ホンミツバチを養蜂しています。
ミツバチは社会性を持つ昆虫で女王蜂一匹に対して~数千匹の働きバチと~数百匹の雄バチで構成されています。
ミツバチは環境監視昆虫ともいわれ、環境学習にも繋がな花に授粉することで一定の植物多様性をもたらすことがあります。
うんな中学校の養蜂場では、セイヨウミツバチを飼っています。センダングサの割合が大きい百花蜜です。

サイエンスクラブのメンバー


渡邉 智也 2年
このサイエンスクラブの部長。好きな教科は、化学と数学。昆虫が好きでよくやんばるに虫取りをしに行っている。昆虫に関してはとても詳しい。ヒメトビサシガメというカメムシの研究をしていたこともある。最近は化学にも手を出している。
座右の銘は「わからないことにルールを探す。その地道な努力を人間は科学という。」

宮田 奏 2年
サイエンスクラブの副部長。石が好きで宝石の名前を覚えている数で右に出る者はいないだろう。好きな石はアクアマリンで、趣味は採掘。体力が少なすぎて作業系は苦手。
座右の銘は「自分の好きを大切に」

小林 誠 2年
自称「やさしい平和主義者」。そしてサイエンスクラブの頭のいい脳筋で,力仕事は彼に任せれば大体何とかなる。好きな教科は、数学。根はとてもやさしいのだが、座右の銘からもわかるように、みんなが誠の自称「やさしい平和主義者」 に対して疑問を思っている。
座右の銘は「ツァーリボンバ(水素核爆弾)」

與那覇 いつみ 2年
祖国がソ連と言う日本在住の日本生まれ日本育ち。ちなみにロシアに行ったことはないらしい。趣味は釣りで、好きな食べ物は寿司。珍しい生き物に出会いたい。最近はソヴィエト連邦に興味があるらしく、よく「ソ連国歌かっこいいよね!」や「スターリンはイケメン」と言いってくることがある。やさしくて人思いなのだが少し将来が心配である。
座右の銘は「運に恵まれるには努力が必要である」

佐藤 さら 2年
サイエンスクラブでは数少ない常識人。動物、特ににネコ科が好き。小説をよく読んでいる。虫が嫌いでミツバチを扱うときはよく休んでいる。将来は獣医師(動物を扱う仕事)になりたい。
座右の銘は「二兎追うものは一兎も得ず」

清水 ひいろ 2年
サイエンスクラブで一番の語彙力を持っている。屈指のマンガ好きで最近は「アンデットアンラック」にハマっているらしい。好きなことは漫画をよんで寝ること。あつ森のようなスローライフをおくりたいと思っている。
座右の銘は「他力本願」
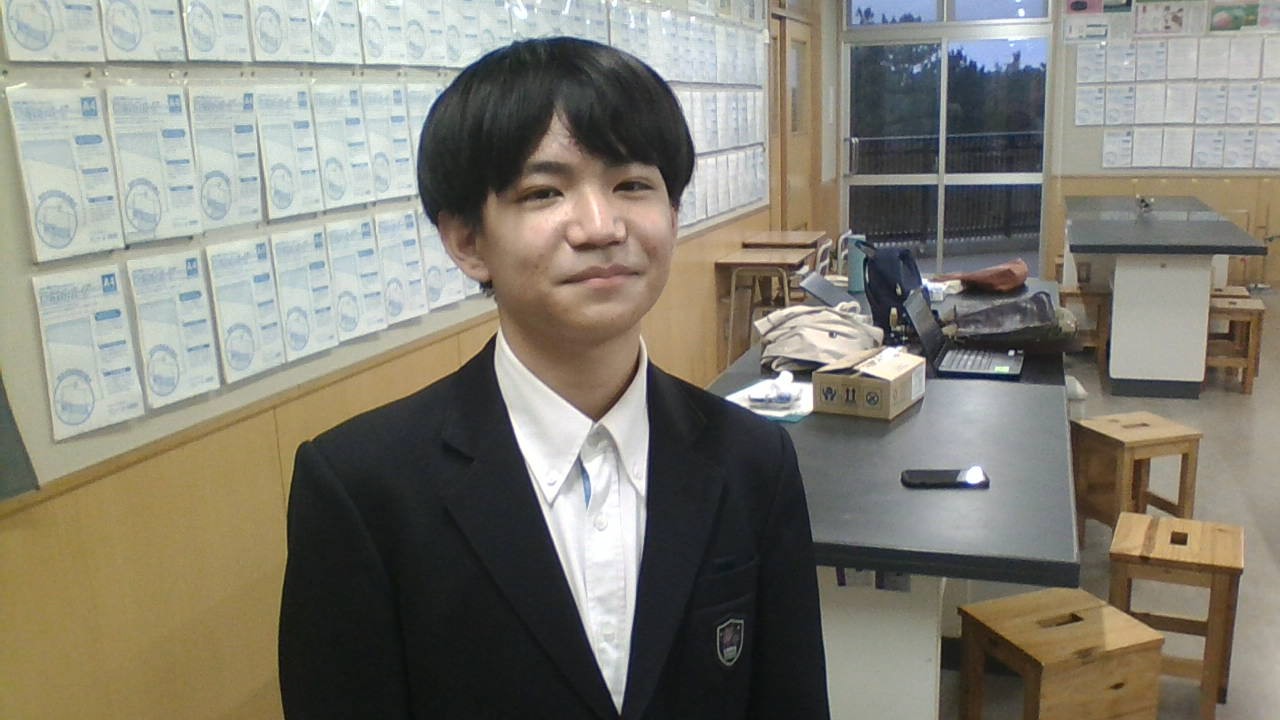
はく 3年
座右の銘は「やる気と金さえあれば大抵何でもできる」

わかな 1年
サイエンスクラブの唯一の1年生。
海が大好きです!
座右の銘「明るく、楽しく、笑顔を忘れず」

サイエンスクラブサポーター
このクラブ活動は、地元の行政・養蜂家・沖縄科学技術大学院大学のスタッフの有志がサポートしています。先ずは、大人が面白がっていろんなことをやってみるをコンセプトに、この活動をサポートしています。
これからも、うんな中学校サイエンスクラブの活動を楽しくサポートしていきます。
サポーター随時募集中でございます!
